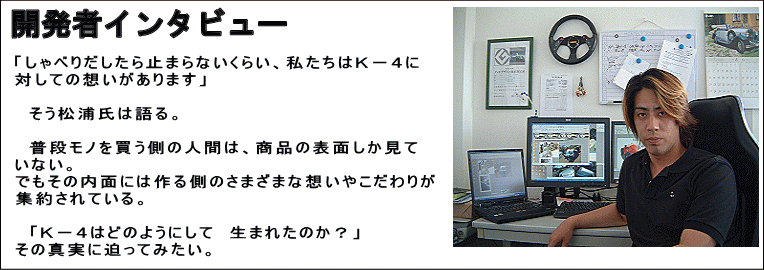
「2STエンジンとしての本当の意味での最後のマイクロカー。
凄いテイストの車ですよ」・・・・・・・松浦氏
光岡自動車横野工場 マイクロ課 松浦 巨英氏に「K−4を訊く」
はじめまして、どつです。
今回は、K−4ファンサイトの作成の許可および、各種情報・画像の提供をして頂いて有り難うございます。
お陰様でなんとか形になってきた感じです。
わたしもK−4ユーザーならば、こんなにも苦労しなかったのですが(笑
是非、買ってください(笑
いやいや、K−3のローンも残っているし、甲斐性無しなので物理的に無理かと(汗
さて、マイクロカーの「集大成」として、作られたK−4ですが「最後のマイクロカー」として出されたTYPE−F、k−3の後になぜ作られたのでしょうか?
なにかK−3などでやり残したことなどあったんでしょうか?
『K-4』の開発を後押ししたのは、やはり『K-3』を発表したときのフィーバー振りでした。
そうですねぇ、、あのときはあっという間にK−3が完売してしまいましたから。
私も発表の次の日の午前中に注文したのですが、すでに43台目でした。
それから2日後にはキャンセル待ち状態でしたし、実際に2週間ほどしてから埼玉のマイクロカーショールームに行ったのですが、まだ戦場のような忙しさでしたね。
しかし、正直K−3の発表は、あたらなマイクロカーということで満を持して・・・という形だったんでしょうねぇ。
いやいや、実を申しますと、『K-3』自体、社内的には大反対されていまして、「マイクロカーでクラシックタイプFを造るなんて馬鹿げてる」という空気が会社全体を占めていました。
ただでさえ風当たりの強いマイクロカー生産に、追い討ちをかけた雰囲気でした。
う〜ん、、マイクロカーの社内の風当たりの強さは、ショールームの鈴木店長からも聞いておりました。
企業ですので利益重視とはいえ会社設立の一因でもあるマイクロカーにとっては厳しい話だったんでしょうね、、、
非常に厳しい状態でした、実際にマイクロカーを担当していた弊社の社員の中からも否定的な意見が出ていました。
「売れるわけが無い」では無く、「造れるわけが無い。」というのです。
確かに全体が丸いMC−1に比べて、クラッシックタイプFはスマートなフォルムですからね。
これまでのマイクロカーでこのようなデザインのものは見たことありませんし・・・。
言われてみれば内部からもそのような意見が出るのは、あり得る話ですね、、、
その時点ではシャシーはほぼ完成しており、後はボディーに合わせてフレームを修正するのみでした。
あ、シャーシーは出来ていたんですか?
はい。
私は会長に呼ばれ、シャシーを見せられて、「みんな作れないといっている。松浦、お前作ってみてくれ。」
といわれたのが始まりです。結果はご存知の通りです。
あの「K−3フィーバー」ですね。
しかし、そこで松浦さんにやらせる会長の決断も素晴らしかったと思います。
このような状況でしたので四面楚歌な状態で造ることになった『K-3』ですが、この追い詰められた空気感が、発表時の会長の言葉である
「これが最後のマイクロカー。」になったと思います。
なるほど・・・・・。
ある意味、会長自身、これで2STエンジンに見切りをつける覚悟だったのかもしれません。ただ、「K-3」の大反響
が、ひとつの指針を示したと思います。その結果、すぐに同フレームの別車種を造る指令が出ました。
おお!四面楚歌の状態から一挙に情勢が変わったんですね。いや〜、なんとも痛快な話です。
いわゆる第二弾の指令です。 私自身、K−3の反響もありまして、これで終わりにしたくなかった想いもあり、まだまだ造りたかったという想いが正直ありました。
この指令はすぐに関係各署に受け入れられ、デザインに着手した次第です。
K−3とは全く別な船出になったんですね。
そんな中、2006/10/22の発表時にはTYPE−RとK−4の併売の予定でしたが、K−4というカタチでリリースした理由はどのようなことだったのでしょうか?
まずは価格を抑えることが必須条件でした。
光岡コンプリートである『TYPE−R』の存続の検討も発表後にされましたが、『K-3』よりコストがかかる『K-4』をコンプリートすると、販売価格が100万円を軽くオーバーしてしまいます。
100万ですか!!う〜ん、、そのくらいにはなるでしょうね。しかし、組み立て工数が10万くらいの差額というのは個人的には安い感じもしますけどね(笑
キットを組めない人向けに「K−4コンプリートサービス」というオプション?を設定しても良かったかも知れませんね。
実際には、少ない人員で回転させられるようにコンプリートを商品から外したのも理由のひとつなんです。
そういや、TYPE−Fの時は、工場の人がものすごい残業で命削って作っていたって鈴木店長が言ってましたっけ。
(笑)
それとですが、『K-3』の販売データを見たときに、キットカーの方の購入問い合わせがやたらに多かったんですよ。
本来であればコンプリート100台、キット100台だったはずが、コンプリート86台、キット114台という変則的な台数になっていました。このことも多少は考慮しています。
え?K−3って100台じゃ無かったんですか??
ウチの車体番号ってKTFE−043/100だったんでそういう刺繍した帽子も作ったんですよ(笑
KTFE−043/114って作り直さないとだめかなー、、、
いや、それはそのままで良いと思いますよ(笑)
それにしても、K−3の販売から異例の早さでK−4が出てきた感じですが、その過程はかなりハードな物だったのではないでしょうか?
『K-4』のプロトタイプが完成したのは、実は2006年の4月でした。
あ、そんなに早い時期に完成してたんですね。
はい。その時点ではヘッドライトも低い位置で取り付けており、通常走行に支障の無い程度でしたが、いきなり耐久走行を行いました。
雨が降っても風が吹いても毎日交代で走り続け、5月18日〜6月30日までに6000Kmを走りきりました。
6000キロですか!!
ええ、途中、何回か排ガス試験をしなければなりませんでしたが、すんなり合格値でしたので、それ以上走らずに済みました。
『K-3』のときは結局1万何千km走りましたが。その蓄積があったので。
6000キロも走ると、何かしらのトラブルが出ませんでしたか?
いや、トラブルはまったく出ませんでした。 もちろん、消耗品というか、ガソリン、オイルの補充、定期的なメンテナンスやエアクリーナー清掃、
フィルター清掃などのみで走りきりました。
耐久走行はそのほとんどの距離を悪路走行、たとえば砂利道やでこぼこ道で行うので、普通のユーザー様が走る条件よりも悪い条件で行っております。
すごいですね〜。
そんな中、10月の発表を迎えたわけですね。
ええ、10月のお披露目に関しても、急遽9月20日ごろ、社内的な事情によりオロチの前座扱いでお披露目をすることとなりました。
さらに、急な話でしたので少ない手持ちの写真を使って、カタログを作らねばならず非常に憤慨したのを覚えております。
・・・確かにあのカタログの写真は(汗
K−4のかっこよさをスポイルしちゃっているような。あ、失礼なことを言ってすみません、、
いえいえ、それで今度の新カタログの製作を行った訳です。
あのカタログはカッコイイですよね。写真に「愛」を感じますよ(笑
お披露目が終わったあとは何をなさっていましたか?
『K−4』発表後はマニュアルとの格闘でした。
夜寝る暇も惜しんでマニュアルを作り続け、最初のデリバリーに何とか間に合わせました。
たしかにマニュアル作りは骨の折れる作業ですよね。
私も仕事で良く作成しますが、手を抜こうと思えばどこまででも抜ける(笑
でもそれでは何も伝わらないので、結局は細かく書かないといけない。
また、マニュアルには膨大な写真が必要になるのでデジカメを握りしめて現場を右往左往しないといけない。
なかなかに大変な作業ですよね。
ええ。そんなさなか作りかけのマニュアルをパソコンの故障でデータが消えたりして酷い目にも遭いました。
ああ、確かにそんな話をメールで頂いたような(汗
横野工場のHPの立ち上げも併せて準備されてましたから、それはそれは大変な状況だったと思います。
それだけ開発過程はハードな状況だったんですね。
はい、正直な話、『K−4』はマイクロ課全員で造り、走り、書き、死ぬ思いで作り上げた車です。
ですから、開発過程がハードだったというのは合っていますね。
K-4が開発スタートしたのが2005年の10月ごろで、試作第一号車が完成したのが2006年の4月、走行試験が5月−6月で、後は量産準備でした。
実質は1年くらいかかっています。
1年ですか・・・。
K−3という土台があっても大変なんですね。このK−3から外観以外で改良したポイントとかってあるんでしょうか?
個人的にはエンジンのメンテナンスがしやすい印象をうけましたが・・・
外観以外では、ボディーとバスタブ(シート座面部分)を分けたこと、エンジンメンテナンスハッチをヒンジ開閉式にしたこと、リヤに小物入れを設置し、
マジックテープで脱着できるようにしたこと。
基本的には組み立てやすさと、メンテナンスのしやすさを狙いました。
『K-3』での欠点や、扱いにくい部分を改良したつもりです。
たしかにK−3に比べるとメンテナンス性は向上してますね。ちょっとジェラシーですよ(爆
(笑)
ところで、デザインの由来は?他にもデザインのアイディアがあったのでしょうか?
鈴木店長からは、コンペ形式で行ったと聞いていますが・・・。
『K-4』のデザインモチーフは1950年代のフォーミュラーカーです。
具体的にはアルファロメオになりますね。
アルファロメオだったんですか。
ええ、デザインアイディアはMC-1、COMBOY88をデザインした渡辺が行いました。
マイクロショールーム側からもアイディアは出ておりまして、オースティンヒーレー(カニ目)を作る案が出ていましたね。
ああ、確かに鈴木店長の好きそうなデザインだ。(カニ目)
最終的にはやはりサイクルフェンダーの魅力が勝ったため、現在の『K-4』に落ち着いたわけです。
なるほど・・。
確かにサイクルフェンダーは乗っていて車のハンドルを切るたびに方向が変わり楽しいんですよね〜。
私もセブンはサイクルフェンダー派です。持ってませんが(笑
さて、K−4の印象を大きく変えてしまった、例のK−4のヘッドライト位置の変更を余儀なくされた保安基準の改訂はいつごろだったのでしょうか?
もし、FRPの型ができた後だとすると大変な作業だったと思いますが・・・。
これについては、まさに晴天の霹靂でした。
『K-3』のときに比べ、ヘッドライトの位置基準が高くなり、それが判明したのが6月です。
実際は2006年の1月くらいからの基準変更だったと思います。
判明した6月時点では生産型は出来ていましたので、型を変更することなく位置の基準に適合させるため苦労しました。
マイクロ課総動員でステーの設計変更等行いました。
総動員ですか!?
はい、認証試験用の書類に掲載する3面写真もヘッドライトが低い位置で作ったものを貼り付けており、試験風景の写真も全て変更でした。
要するに弊社が情報収集をぬかってしまったために起こった事態でした。
ところで、K−4とは関係ないのですが光岡関連のホームページでMC−1&Tの販売終了は明言化されてますが、K−1も販売終了してしまったのでしょうか?
K−4に注力するため一時的なオーダーストップだと信じたいのですが・・・・。
これは言いにくいのですが、MC-1の販売終了と同時に、K-1も終了しています。
長い間MC−1とK−1を愛して頂き、ユーザーの皆様に対しては本当に感謝しております。
う〜ん、仕方のない事とはいえ、悲しいなぁ・・。憎きは排ガス規制か。マイクロカーくらい免除してくれてもいいのになぁ・・。
ほんとうです(笑)
あ、前から気になってたんですけど、テレビ東京のWBS(ワールドビシネスサテライトで)『K−4』のお披露目をしたときに、松浦さんが「すごいテイスト」を言われていましたがその意味は何なんでしょうか?
ああ、『すごいテイスト』の意味は、この『K-4』というキットカーを手に入れられた方がメーカーになれるという醍醐味に集約されると思います。
マニュアルにある基本完成形は「踏まえていただかないといけませんが、基本完成形で乗るもよし、さらにオリジナリティーにあふれた形で昇華させてもよし、といった意味で、どこが完成かという明確な線引きはありません。
販売している私共が見ても、ついいじりたくなってしまう魅力がこのキットカーにはあります。
あそこをこうして、ここをああして・・・などと空想するだけでも楽しくなってきますし、また、「自分で作り上げたキットカーを、自分で登録する。」
これはキットカーの理念なのですが、ある意味すごいことだと思いませんか?
思います!思います!(笑
さらに、このキットカーというモノを媒介したネットワークが構築されること。
お互いのキットカーのできばえにリスペクトされながらさらに自分のキットカーを昇華させていけるというか。
何というか、この辺の深い部分を総称して「すごいティスト」と言ってみました。
通常の車両ではありえない。でも実際そんなことが出来る。これがキットカーだと言うことで。
なるほど。マイクロカーのユーザーで、キットカーも認知している私たちにとっては当たり前なことでもTVを見ている不特定多数の人にとっては判らないことですもんね。
それで凄いテイストなんですね。
そうです。
かなり時間も過ぎてしまったので、最後に一言お願いしたいのですが・・・。
2STエンジンとしての本当の意味で最後のマイクロカーとなるこの『K-4』を、ぜひ皆様にも味わっていただきたいと思います。
既にユーザーとなっている方も、そうでない方も。本当に「すごいティスト」ですよ。
なんか、もの凄く味わいたくなりました!!
インタビューを終えて。
マイクロカーを語る松浦さんはとても熱い人でした。
それは、マイクロカーを支えているマイクロ課の皆さんもそうであると感じました。
「マイクロカーにかける気概」
それは、他の自動車メーカーではやっていないという誇りと、ユーザーに対して通常では経験出来ない「自分で車を組み立てて、自分で登録し走らせる」というとてもエキサイティングな経験を提供していきたいという想い。
かつて、光岡進会長が自分で作った車を陸運支局に持ち込んで認可をとり公道を走った喜び。
その喜びをメーカーとしてアシストしユーザーに提供しているのがマイクロ課の皆さんだ。
こんなこと、世界の名だたる大メーカーのトヨタやGMでもやっていない。いや、出来ないであろう。
キットカーを作ったことのある人ならば判るとおもうけど、自分で車を作る体験と、公道を走れる車が手に入るならばマイクロカーの値段というのは決して高いものではない。
よく軽自動車と比較されるけど、こっちは「体験付き」なのだ。
キットカーを組み立ての体験をした時の感動はお金には替えられない素晴らしいものであった。
モノ作りが衰退していると言われる現代に対してのアンチテーゼ。
札幌で銅像になっているクラーク博士が現代に生きていたら「若者よキットカーを造れ」と言ったに違いない。

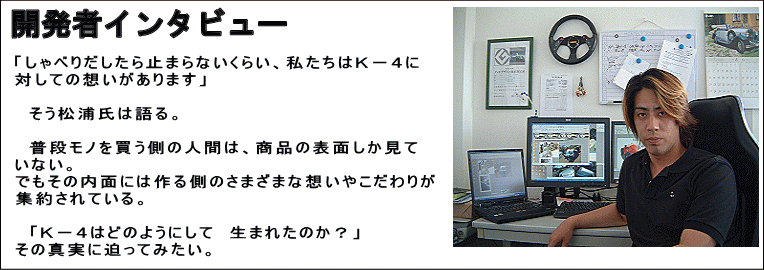
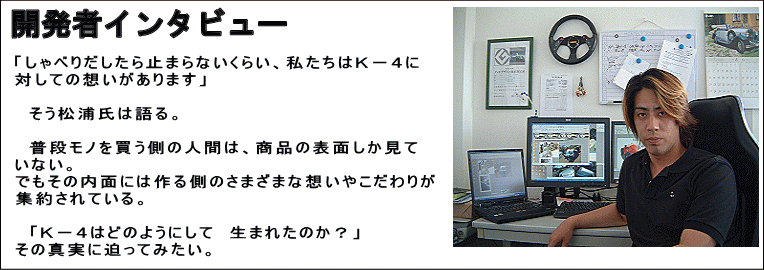
![]()